| アトピー |
| アトピーは、アレルギーにより皮膚炎が起こり、痒みを生じる病気です。慢性再発性の痒みを特徴とし、本人も夜眠れなくなったりして、動物も見ている家族の人もつらい病気です。 |
 |
||||||||||||||||||||
| 直接の原因は、アレルゲンに対しての過剰な免疫の獲得によって、皮膚で炎症が起こってしまうことです。健康状態なら過剰な反応が起こらないような物質に対してアレルギー反応を示してしまうことにより、アトピーの症状が生じます。 |
 |
||||||||||||||||||||
| 人間はアレルゲンを呼吸器から吸入することが多いですが、犬においては、アレルゲンは接触によるものが多いです。 |
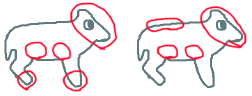 アトピーの部位 食物アレルギーの部位 |
||||||||||||||||||||
ケアンテリア、ウェスティ、ラサアプソ、ダルメシアン、パグ、アイリッシュテリア、ブルテリア、ゴールデンレトリーバー、ボクサー、イングリッシュスプリンガースパニエル、ラブラドールレトリーバー、ミニチュアシュナイザー、柴犬が遺伝的素因を持っているといわれますが、他の犬種でも起こります。 特徴は 1~3 才での発症、慢性再発性の皮膚炎、 夏と秋に増悪(→通年に移行)する、外耳炎や皮膚の 細菌感染の併発などです。 皮膚炎の起こりやすい場所は、顔の周り、四肢の 先端、そけい部、脇の下の周囲などです。 体の痒みを起こす病気は他にもいくつかあり、鑑 別診断はノミやアカラスなどの寄生虫、皮膚の細菌 感染症、脂っこい犬種の脂漏症、アトピーや食餌/接触アレルギーなどのアレルギー疾患、etc です。 中でも食物アレルギーはアトピーとよく似たアレルギー疾患ですが、 アトピーよりも若齢(1 才令以下が多い)で発生する、症状の場所が異なる、 下痢・軟便・瀕回の便が見られることがあ る、などといった特徴を持ちます。 アトピーの直接の原因はアレルギー反応を起こしやすいという体質ですが、 いくつかの要因が 重なることによって、症状はさらに悪化します。体の中で痒みが起こる原因は、 よく「コップの理論」で説明されます。それは、感染やアレル ゲン、ストレスや外部環境などの要因が積み重なって行って、本人の許容範囲を超えると痒みが 出て来るという説明です。 |
|||||||||||||||||||||
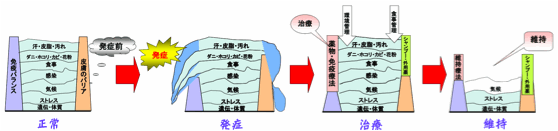 |
|||||||||||||||||||||
| 健康状態では、免疫バランスと皮膚のバリアがしっかりしていれば、簡単には炎症は起こらな いのですが、アトピーの状態ではコップの外側が低くなったような状態になっていますので、刺 激の要因が増えて来ると、コップから水が溢れ出すように許容範囲を越えてしまい、炎症が起こ って痒みを引き起こすことになります。 | |||||||||||||||||||||
| 免疫バランスで最近注目されているのが Th1/Th2 バ ランスという考え方です。体の中には、Th1(ヘルパー 1)型と Th2(ヘルパー2)型の免疫反応があり、それ ぞれ、 Th1:細菌やウイルスなどに反応して細胞性免疫を誘導。 Th2:カビやダニなどに反応して IgE 抗体を産生し、液性免疫を誘導。 |
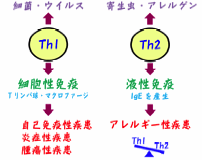 |
||||||||||||||||||||
| という役割を持っており、バランスが取れた状態で体の免疫が保たれています。 Th2反応に体が偏ると、アレルゲンに対するIgE産生の過剰によって、体の中で炎症反応が進行し、アトピーなどのアレルギー疾患が発生しやすくなります。 初期の赤い病変ではTh2反応が優勢ですが、長期慢性化して黒く分厚くなった病変では、慢性的な細菌感染などでTh1反応が刺激されて増加し、複雑な状態となってきます。 皮膚を守る要素としてもうひとつ大切なのは、皮膚のバリアです。 正常な皮膚では、外部刺激をブロックし、体内の水分を逃がさないようにするためのバリア構造がしっかりしており、皮膚の健康が保たれているのですが、アトピーのときには皮膚のバリアがダメージを受け、外部刺激が入りやすく、体内の水分が外部に逃げやすい状態になってしまっています。 アトピーの直接的な原因となるのは、アレルギー反応の引き金となるアレルゲンの存在です。アトピーのときには、体内で作られたIgE抗体が肥満細胞と反応して炎症物質を放出し、それが皮膚に炎症を起こします。 何のアレルゲンに反応するかは個体によりそれぞれですが、アレルゲンには季節性のものと非季節性のものがあります。季節性のものとしては花粉などがあります。一方、非季節性の80%はカビ・ホコリ・タバコ・上皮・除虫菊・ホコリダニと報告されています。 アレルギー体質の動物においては、多くの場合、複数のアレルゲンに対して反応を示します。 アトピーの診断は、臨床症状と病歴から可能性を疑い、IgE抗体の検査を行うことで確定する、という手順になります。以下の表の通りの項目で、大定義と小定義がそれぞれ3つ以上該当すれば、アトピーが疑わしい、ということで暫定診断となります。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 症状からアトピーなどのアレルギー疾患を疑ったら、IgE抗体検査を行うことによって、アレルギー疾患の確定とアレルゲンの同定を行います。アトピーの診断をつけ、アレルゲンの回避や減感作療法を行うにあたってはアレルゲンの同定が必須ですので、アトピーを疑う場合はIgE検査をしておくことが推奨されます。 |
|||||||||||||||||||||
| アトピーの原因は単一ではなく、複数の原因が関係していることがしばしばです。 アトピーの症例のうち、約3割は環境アレルゲン以外に、食物やノミなどにも反応していると報告されています。 |
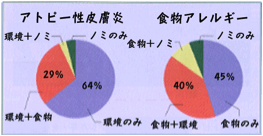 |
||||||||||||||||||||
| アトピーは、診断がついても、それですんなり治療してすっきり良くなるという病気ではありません。いずれの治療を行っても、長いおつきあいになることは避けられない病気ですので、飼い主さんにも腰を据えておつきあいをしてもらう必要があります。 治療にあたってまず大切なのは、炎症と痒みを悪化させる要因を減らして行くということです。刺激の総量が閾値を超えたときに痒みが発症しますので、併発症や痒みを起こす他の病気があるときには、そちらのコントロールをすることも必要です。 特に気をつけるのはノミやカイセン、アカラスなどの寄生虫、細菌やマラセチアなどの感染症、内分泌疾患などです。 併発症をコントロールしたら、IgE検査の内容をもとにアレルゲンの回避を考慮します。 アレルゲンには食餌由来のものと環境由来のものがあります。 食物がアレルゲンとなっている場合、アレルゲンを含んでいないものに変更します。 環境アレルゲンに対しては、屋内のアレルゲンであればこまめに掃除を行ったり、屋外のアレルゲンであれば室内飼育にする、ということも考えます。アレルゲンは皮膚からも吸収されますので、散歩の後にタオルで体を拭いてアレルゲンを除去するということも有用です。 体質改善のために、とても重要なのが食餌です。食物アレルゲンが原因になっているのであれば、アレルゲンを含まない食餌に変える必要があります。 さらに、食餌によって、体を炎症が起こりにくい体質に改善することが可能です。体の中で痒みを起こす物質というのは体の脂肪酸(ω6脂肪酸)から作られるのですが、エイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)といったω3脂肪酸を含んだ食餌をとることにより、痒みを起こしにくい体質にすることができます。 それぞれの会社毎、製品毎に、使用しているタンパク源が異なりますので、IgE検査を行った後は、IgE検査の結果をもとに食餌を決定することになります。 シャンプ―療法もアトピーの治療では重要です。 アレルゲンは食餌以外に、皮膚を通しても体内に吸収されるのですが、こまめに洗うことにより、皮膚についたアレルゲンを洗い落とすことができます。 また、シャンプ―療法は、皮膚の感染のコントロールと皮膚バリアの修復のためにとても有用です。中でも、アデルミルというアトピー用に開発された治療用シャンプ―は、皮膚を保湿し、炎症を鎮め、アレルゲンを吸着して体に吸収されにくくするという効果を持っていますので、アトピーのときには特に推奨されます。 薬物療法は、対症療法と免疫療法に分かれます。 対症療法は、病気自体の治療ではなく、症状を抑えることを目標とする治療であり、そのために用いられるのがステロイドやサイクロスポリンなどの免疫抑制剤です。対症療法の目指すところは、炎症のコントロールをして痒みを和らげ、QOLを向上させるということです。 ステロイドは、昔からアレルギー疾患のコントロールに用いられて来た薬ですが、長所は、即効性、確実性がある(飲んだら飲んだ分効くということです)ことと、短期的に見ると治療費が安いことです。 短所としては、薬をやめると再発してしまうため、薬を継続する必要があることと、長期にわたってステロイドを使用することにより、副作用の心配が出てくることです。 サイクロスポリンは最近出て来た薬ですが、アトピーに高い確率で効果があり、かつステロイドよりも副作用が少ないためアトピーでも使いやすい薬です。効果は高いのですが、やや高価です。導入時は約30日間、毎日服用しますが、一ヶ月して効果が出てくれば、使用回数を減らして行くこともできます。 抗ヒスタミン薬は、かゆみが起こらないように予防するのに有効ですが、犬においては約20〜50%の効果とされています。炎症が強いときに使っても効果は弱いので、一旦炎症を抑えてから使用するようにします。副作用はとても少ないです。 その他、皮膚の状態を良くするためのサプリメントも各社から発売されていますので、使用してみるのも有効かもしれません。 最近登場した選択肢としては、減感作療法というものがあります。これは、アレルゲンを希釈した液を微量から少しずつ注射して行き、いわば、「アレルゲンに体を慣れさせていく」という治療です。体内の免疫をバランスの取れた状態に誘導することによって病気を根本から治療しますので、アトピーの治療法の中では唯一、根治につながる可能性のある治療法です。 抗体検査を行いアレルゲンを確定した上で、その結果に合わせて減感作薬を作成し、低用量から徐々に注射を行って行きます。 反応としては60〜80%とされています。約9ヶ月の導入により良好に反応したら、以降は月に一度ずつの注射で治療を継続して行きます。 手間ひまと時間がかかる治療法ではあるのですが、若くて、赤い急性炎症を持っている子では、ステロイドの副作用を避けるためにも、選択肢として考慮してみる価値はあります。 いずれの治療を取るにしても、ひとつの治療によって全てうまくいく、というものではありませんので、皮膚の状態を見ながら、各種の治療を組み合わせて治療を続けて行くことになります。 |
|||||||||||||||||||||

