| 犬の分娩 |
| 犬の妊娠期間は約63日(正確には排卵日から63日です。排卵前後のいつ交配したかで日数が変化します。)です。犬は比較的安産をすることが多いですが、特に短頭種などでは帝王切開が必要になる可能性が高くなりますので、分娩予定日を予想して獣医師とともに心構えをしておく必要があります。なお、妊娠56日以前の分娩は早産であり、死亡率が高くなります。 分娩の7〜10日前に出産場所に移動しますので、安心できる場所を用意してあげ1週間前からそこに慣らすようにしてください。あまり構い過ぎない方がいいですが、飼い主に強い愛着を持つ犬では逆に飼い主のそばで出産したがることもあります。最後の1週間に体温が0.5〜2℃下降します(犬の平均体温は38.5±0.5℃、ただし個体差あり)ので、妊娠が確認されたら妊娠後半から1日1回ずつ直腸温を測定していった方がいいでしょう。犬の分娩は以下のステージに分かれて行われます。 |
||||||
第1ステージ:準備期 行動や精神状態に変化が現れます。分娩12-24時間前から体温がさらに0.5〜1.0℃低下し、まもなく分娩が始まります。子宮頚管の拡張と膣の弛緩が起こり、分娩の準備をしている段階です。神経質になり始めますので、構い過ぎないようにし犬を落ち着かせます。 |
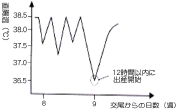 |
|||||
第2ステージ:新生子の娩出期 体温は通常の温度に戻ります。腹部の緊張(陣痛)が観察されます。産道を通る途中で尿膜が破裂し、透明な液体が陰部から出てきます。 |
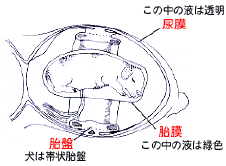 |
|||||
| 通常陣痛開始10〜30分以内に第1子を娩出します。このステージは全体で2-12時間です。緑の液体は胎膜破裂の徴候ですので注意が必要です。 このステージで「低下した直腸温が通常温に戻っても分娩の兆候が見られない。緑色の液体が出ているが胎子が見えない。透明な液体が出てきてから2-3時間経過しても胎子が見えない。微弱で不規則な陣痛が2-4時間持続。強く規則的な陣痛が20-30分持続 。最後の娩出から2-4時間経過。12時間以上第2ステージが持続」といったときには検査が必要です。 第3ステージ:胎盤の排出と子宮角の収縮 胎盤は通常子犬に続いて45分以内に出てきます。胎盤を食べると嘔吐することが多いので食べる必要は特にありません。子宮角の収縮は各胎子の娩出後15分以内に起こります。 分娩全体は通常全体で4-6時間のことが多いですが個体差があります。分娩後悪露は犬では緑色で約4-6週間続き、最初の1週間が最も量が多いです。子宮の回復には12-15週間かかります。 分娩中に「1頭も産まずに2時間以上間欠的な陣痛収縮が続く。1頭も産まず集中的に持続的な陣痛が続く。1回毎に中途半端な緊張で胎子もしくは水袋が出現してから30分が経過」の場合には検査が必要です。 また分娩後に「分娩後4-6時間たつが全ての胎盤の排出がまだ。悪露の腐敗/悪臭。子宮からの出血が持続。直腸温が39.5℃以上。母もしくは子の様子が変」といった状態では検査が必要です。 難産 母体側に原因があるもの(約75%:うち約70%が子宮無力症、残り5%が産道狭窄、子宮捻転.etc・・)と胎子側に原因があるもの(約25%:うち約15%が胎位異常、残り約10%が奇形、過大胎子、胎子死亡など)とがあります。 |
||||||
| 子宮無力症: 胎子数が少ないために分娩への刺激が足りない、もしくは胎子が多い/大きいために子宮の筋肉がのびきって力が入らないことなど.etcが原因です。初産で神経質なコの場合には精神的なものの場合もあります。 |
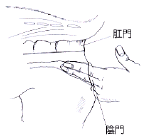 |
|||||
| 腹部の緊張を促すためにまず20-30分飼い主と一緒に運動をします。それで反応がなければ膣に指を入れ、膣の上部をなぞるようにして刺激を加えます(フェザーリング)。それでもだめならカルシウム剤の注射、子宮を収縮させるオキシトシンの注射を考慮します。反応がない場合や一刻を争う場合には帝王切開手術となります。 | ||||||
| 胎位異常: 通常胎子は分娩中に体を動かして、自分で分娩しやすい胎位になります。正常な体位の約60%は前足を前に出して子宮の出口を向いた頭位ですが、犬では後肢とお尻が出口を向いた尾位も正常とされています。ただし尾位では産道の拡張刺激が弱くなることと毛の向きが進行方向と逆のため、頭位よりも難産になりがちです。 |
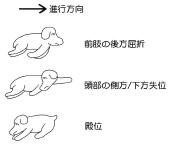 |
|||||
| 胎子が弱っている場合には胎位がうまく整わずに胎子異常(主にイラストの3つが多い)となることがあります。また複数の胎子が子宮の途中でつかえて出られなくなることもあります。途中まで出てきていれば引っ張って出せることもありますが、途中でつかえて出てこないことは帝王切開手術となります。 過大胎子: 胎子が1頭の場合、過大胎子となり難産しやすくなります。 分娩後の病気 子宮からの出血: 正常な分娩でもわずかな出血は普通に見られますが、出血量が多いときには子宮の裂傷、血管破裂、出血傾向の体質などが疑われます。 胎盤停滞・停留胎子: 分娩後に胎盤が排出されずに残ったり、死んだ胎子が子宮の中に残った場合には母胎に重大な問題となることがあります。どす黒い膣からの排出物や一般状態の悪化が見られます。 無乳症: 不安などにより乳汁の排出が低下する場合があります。乳量が低下すると新生子の体重が増加しません。栄養や一般状態の悪化がないか確認して、安心できる環境をつくります。注射で治療する場合もあります。 産褥性テタニー(低カルシウム血症): 授乳によりカルシウムが足りなくなったことが原因です。分娩後の21日以内に起こることが多いです。落ち着きが無くなり、呼吸が荒くなり、ふらふらしはじめ、悪化すると神経症状、発作を起こします。意識が無い状態までなると命に関わることも多いので早い処置が必要です。 その他、子宮や乳腺に関係した病気がいくつかあります 周産期の栄養について 犬のカロリーの必要量は以下のグラフの通りに変化します。妊娠中、胎子の体重が増加するのは妊娠後半からなので、妊娠5週目あたりからすこしずつ増やしていけば良いでしょう。ただし、過食によって肥満すると難産の原因になりますので注意してください。妊娠したからといって極端にゴハンの量を増やす必要はなく、カロリー必要量が増加するのは妊娠後半から授乳終了までです。授乳中は栄養をしっかり取らないと低カルシウム血症になることがありますので気をつけてください。妊娠・授乳期用のフードもありますのでそれを使用するのも良いでしょう。 |
||||||
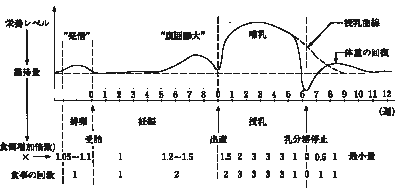 |
||||||
| 新生子の看護 子犬が生まれると、通常母親は鼻の周りの胎膜をなめ取る、体温上昇のために鼻をこすりつける、臍帯をかみ切る、授乳を促すといった母親行動を示します。これらをしない場合には人間の介助が必要なことがあります。 |
 |
|||||
| 新生子の看護 子犬が生まれると、通常母親は鼻の周りの胎膜をなめ取る、体温上昇のために鼻をこすりつける、臍帯をかみ切る、授乳を促すといった母親行動を示します。これらをしない場合には人間の介助が必要なことがあります。 |
||||||

