| 減感作療法 |
| アトピーと言うのは、花粉、カビ、動物、ダニなどのアレルゲンに反応して体に炎症が起こる病気です。一番の特徴は慢性再発性の痒みですが、アトピーは従来、「治らない病気」と考えられてきました。 減感作療法と言うのは、アトピーの治療法のひとつで、体の中の免疫バランスを良好な状態に誘導することによって、体の中でアレルギー反応が起こりにくいように持って行くと言う、比較的新しい治療法です。 アトピーの治療は、対症療法と免疫療法(減感作療法)に分かれます。 対症療法は、病気自体の治療ではなく、症状を抑えることを目標とする治療であり、そのために用いられるのがステロイドなどの免疫抑制剤です。対症療法の目指すところは、炎症のコントロールをして痒みを和らげ、QOLを向上させるということです。 ステロイドの良いところは、即効性、確実性がある(飲んだら飲んだ分効くということです)ことと、短期的に見ると治療費が安いことです。短所としては、薬をやめると再発してしまうため、薬を継続する必要があることと、長期にわたってステロイドを使用することにより、副作用の心配が出てくることです。 ステロイドや免疫抑制剤の内服に加え、アレルギー用の食餌への変更、アレルゲンからの回避、シャンプ―療法で皮膚バリアを良好に保つ、ということを組み合わせて行くというのが、伝統的なアトピーの治療の基本です。 症状を抑えることを考える対症療法に対して、アレルギーを免疫的に、根本から治療をしようと考えるのが減感作療法です。減感作療法と言うのは人間の花粉症治療にも広く用いられ、犬のアトピーでも最近用いられるようになって来た治療法ですが、アトピーの治療の中では唯一、根治に至る可能性を期待することのできる治療法です。 海外ではすでに、アメリカ国内および約30カ国で年間3万セット以上が使用されており、日本でも近年注目されて来ている治療です。 長所は、免疫のバランスを良い方向に誘導することによって、薬に頼らず根治が可能となるかもしれないという点と、ステロイドに頼らない治療ができれば、ステロイドの副作用の心配がなくなるという点です。 短所は、後述する通り、手間ひまがかかるので、飼い主さんの理解と協力が不可欠であるという点と、導入期の初期費用は対症療法よりもコストがかかるということです。ただ、維持期まで到達すれば注射の頻度も減りますので、長期的なコストはむしろ減感作療法の方が安くなるかもしれません。 減感作療法の機序はまだ全てが明らかにはなっていないのですが、主に考えられているメカニズムは以下のふたつです。 |
||||
| ひとつ目は、IgGとIgEの関係です。 アトピーと言うのは、体の中でIgE抗体が過剰に増加し、それがアレルギーを引き起こす原因になっているのですが、減感作療法を行うと、IgGというアレルギーの原因とならない抗体の増加を誘導します。 増加したIgG抗体は、アレルゲンがIgEに捕捉される前にアレルゲンを吸い取る役割をしますので、結果としてIgEによるアレルギー反応が起こりにくくなるとされています。 |
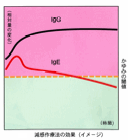 |
|||
| さらに最近、アレルギー疾患では、Th1/Th2バランスという言葉が注目されるようになって来ています。 ヘルパーT細胞(Th)というのは免疫をコントロールする役目を果たしている細胞ですが、ヘルパーT細胞には1型(Th1)と2型(Th2)があります。 |
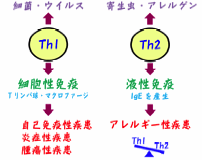 |
|||
そのうちのTh1は細菌やウイルス、腫瘍細胞に反応する細胞で、キラーT細胞やマクロファージの増殖・活性化を刺激して細胞性免疫(免疫細胞による直接攻撃)を誘導します。 一方、Th2は寄生虫やアレルゲンなどに反応して増殖する細胞で、Bリンパ球の増殖と分化を刺激することによって、液性免疫(抗体を産生して外敵を攻撃)を誘導します。 体の中では、Th1とTh2がバランスを保つことによって免疫が正常に保たれているのですが、Th1とTh2のどちらに偏っても、免疫のバランスが崩れ、病気の状態になってしまいます。 Th1が過剰になったときには、自己免疫性疾患、炎症性疾患、腫瘍性疾患の発現が起こりやすくなります。 一方、Th2が過剰になり、IgE抗体が作られすぎると、それによってアトピーなどのアレルギー疾患が起こりやすくなります。 アトピーにおいては、Th2に免疫バランスが傾き、アレルゲンに対して過剰なIgEが産生され、それによって体内で炎症が起こっている状態になっています。 減感作療法を行うことによって、Th2側に傾いてしまった免疫バランスがTh1方向に引き戻され、免疫のバランスが取れている状態に誘導されると考えられています。 減感作療法を行うにあたっては、まず採血を行って外部検査センターにIgE検査を依頼し、92種類のアレルゲンに対しての反応(抗体価)を調べます。 反応するアレルゲンが分かったら、そのデータをもとにオーダーメイドで減感作薬を作成し、それを低用量から注射して行きます。 |
||||
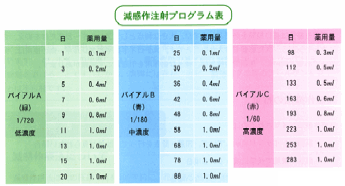 |
||||
最初の導入は、緑液→青液→赤液と、徐々に濃度と量を上げて行きます。 スケジュールは右の表の通りで、約9ヶ月(計26回)かかって用量を増やして行きます。赤液のプロトコルまで終了したら、あとは1ヶ月毎に維持液として赤の濃度の維持液を注射して続けて行くことになります(バイアルの更新時には念のため、半量に減らして注射します)。 |
||||
| 副作用として考えられるのは痒みの増加、嘔吐、下痢、じん麻疹などですが、その中で最も気をつけなければいけないのはアナフィラキシーの発現です。減感作注射はアレルゲンを希釈した液を低用量から注射して行く治療ですが、体が過敏に反応すると、アナフィラキシー反応が出る可能性があります。 |
 |
|||
発生する可能性は低い(0.005%)ですが、注射を打って30分は院内で様子を見ておいた方が無難です。ちなみに、アメリカのラボの調べでは、今までの約30万頭の症例において、死に至ったケースは今のところゼロとのことです。 用量を増やして行く過程で痒みなどの症状が出た場合は、一旦段階を落とし、用量を減らして再接種を試してみることになります。また、予定よりも低い濃度で維持を行う可能性もあります。 必ずしも表の通りに進行するとは限らないので、進行のスケジュールは個体の状態に合わせて行うことになります。 減感作療法の効果としては、60〜80%の個体において改善が見られるとされています。 効果を妨げる要因として考えられるのは、高齢、免疫低下〜不全状態、判明していないアレルゲンへの反応、他の慢性疾患などです。 あまりにアトピーが慢性的になり、細菌感染も重度となって、体に強いTh1反応も起こるようになってしまった状態(皮膚が黒く、分厚くなってしまった中齢以降)では、減感作療法も効きにくいと言われています。 一番減感作療法が効果を期待できるのは、体がTh2側に傾いていると予想される、若くて赤い炎症がおきている状態の動物です。 減感作療法は、これだけで全てがうまくいくという万能の治療ではありませんので、食餌療法や感染のコントロール、シャンプ―療法、アレルゲンの回避など、他の治療と組み合わせて行っていく必要があります。 若齢から発症し、ステロイドを慢性的に飲み続けるようになってしまったような場合、ステロイドの副作用も心配になってきます。 まだ若く、これから十年以上寿命のあるという動物の場合は、ステロイドに頼らず、根治を目指す治療である減感作療法のメリットというのは大きなものになると考えられます。 慢性的な痒みでお困りの方は、有力な選択肢として、減感作療法を積極的に検討してみる価値があると思います。 |
||||

