| 出血傾向 |
| 出血傾向とは正常な個体よりも血が止まりにくいために出血が続く状態です。止血は 出血→血管収縮 →血小板活性化・凝集(一次止血) →フィブリンによる血栓の安定化(二次止血) という複雑なメカニズムとたくさんの因子によって行われるため、どこかに異常があると障害が起こります。 |
||||
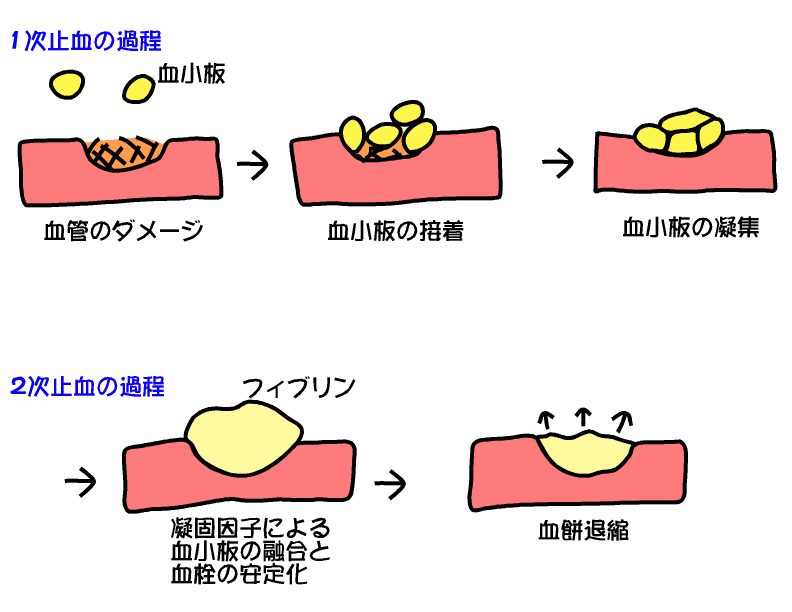 |
||||
| 1次止血: 血小板の凝集により傷害を受けた血管部分をふせぎます。 血小板障害、フォン・ウィル・ブランド病(VWD)、血管疾患などにより1次止血障害が起こります。 血小板栓子が形成されないため少量出血しますが凝固因子によるフィブリン塊が形成され血液凝固が起こります。典型的な出血の仕方は点状出血・斑状出血(小さな出血)です。 検査:出血時間、血小板数/機能、VWF濃度など。 2次止血: 凝集因子による血小板の融合とフィブリン形成による血栓の安定化が起こります。 凝固因子異常により2次止血障害が起こります。 血小板栓子ができてもフィブリンによる安定化がなされないため栓子の崩壊・出血が起こります。典型的な出血の仕方は血腫・関節出血(大きな出血)です。 検査:PT,APTT,TT,PIVKAなどの凝固因子テストを行います。 3次止血: 線溶系が働き、血栓を溶かす過程です。通常止血が達成された後に働きますが、線溶系が亢進すると出血傾向となります。 DICでは血液凝固と線溶系が同時に亢進し、微少血栓が多発しながら出血傾向になります。 検査:血餅退縮時間 |
||||

