| 犬のワクチン |
| 犬の世界には感染すると死亡率の高い恐ろしい病気がまだあります。例えば人で致死率10%だと、社会的に大問題となりますが、ジステンパーだと発症したときの死亡率は50-90%と言われています。ワクチンをうって抵抗力を高めておくことにより、ウイルスが体に入ってきても、症状や死亡率を最小限に押さえることができます。 |
|||
| ●子犬のワクチン 子犬は生まれてすぐにお母さんの初乳を通じて移行抗体をもらい、病気に対しての抵抗力を身につけます。そのため生まれてしばらくは伝染病への抵抗力を持っているのですが、生後時間とともに抗体価が徐々に低下して行き、感染を防げなくなってしまいます。 |
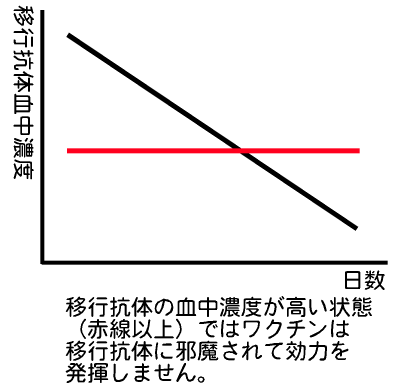 |
||
| 移行抗体が下がった状態でウイルスが侵入してくると、ウイルスを撃退することが出来ず病気を発症する危険性が高くなってしまいます。移行抗体が低くなったら間をあけずにワクチンをうたないといけません。しかし一方で移行抗体が高い状態ではワクチンをうっても移行抗体に邪魔をされ、効力を発揮しません。 移行抗体の下がり方については、お母さんからもらっている量や個体差により異なります。またローレスポンダーといって、移行抗体がある程度低いのにワクチンをうっても抗体価の上がり方が低い個体もいます。 従って、子犬では間隔をあけて最低2回ワクチンをうちます。そうすればワクチネーション終了後の抗体価が十分であることが望めます。 もし3ヶ月過ぎでうつ場合には1回でもいいですが、2回うった方が免疫力がよりしっかり付くという意見もあります。 ワクチンによって得られた抗体価は徐々に下がってきて、やがて病気を予防できなくなる値になってしまうので、1年ごとに注射して抗体価を維持していきます。 なお、不特定多数の子犬が集まってくるところや伝染病の心配のある環境に子犬を導入する場合には、4〜6週令でジステンパーとパルボの2種混合ワクチンをまずうっておく方法もあります。 初乳をしっかり飲んでいるコを一般家庭で飼う場合には1回目のワクチンは生後7〜9週、2回目のワクチンを生後10〜12週(できれば90日以上)でうつ方法でも結構です。 ●ロータイターとハイタイター タイターというのは力価(ウイルスの攻撃力≒ワクチンの効力)ということです。従来のワクチン、特にパルボワクチンは母犬からもらった移行抗体がしっかり下がらないと効果を発揮しにくいものでした。そのため、ロータイターという種類のワクチンを用いた場合はパルボに関しては4ヶ月目でもう一度追加接種をした方が良いとされていました。 最近はある程度移行抗体が残っていても効果を発揮しやすいハイタイターというワクチンが主流になっています。これを使うと3ヶ月令の時点でうっても効くといわれているのですが、高力価の影響で、特異体質を持っているコにおいてはアレルギーの作用が若干出やすいかもしれないといわれています。念のため、最初の接種後は病院内で15分ほど様子を見ておいてください。 ●社会化期とワクチン 犬の社会化期は4-12週の間です。その間が新しい人・動物・ものに馴れやすい時期です。そのためこの時期にいろんな経験をさせることはそのコの「犬格」育成にとても重要なのですが、一方で感染症にかかってしまう危険性があるため、他の犬との接触には危険がついてきます。それを頭に入れた上でいろんな経験(他の人に会わせたり、車に乗せたり音を聞かせたり)しましょう。本格的な散歩は最後のワクチンが終わって2週間以上たってからです(接種後の抗体価の上昇はパルボで1週間、ジステンパーで3週間と言われています)。ワクチンをうっても抗体価があがるには時間がかかります。ワクチン接種がまだだけど移動させないといけない、あるいは不特定多数の犬と接触させたいという場合には事前にインターフェロンを注射して、体を抗ウイルス状態にしておく方法もあります。 なお、4-8週は楽しいことを中心に覚える時期ですが、8-12週は怖さを学びやすい時期です。叩いたり、怒ったりはしないように注意しましょう。2回目のワクチンをうつ時期はちょうど怖さを覚える時期と重なるため、病院でいやな思いをしないように気をつけて、注射の後はうんと褒めてあげて下さい。 ●ジステンパー ウイルスによって起こる病気で、死亡率も高い(50-90%)恐ろしい病気です。症状は慢性経過をたどり、いろんな症状を起こします。咳、鼻水、嘔吐、下痢、原因不明の発熱、ハードパットや「分からないが具合が悪そう」な症状などを経て神経症状、死亡をおこします。何とか助かっても歯のエナメル形成不全を起こしたり、神経症状が一生涯残って寝たきりになったりする後遺症状を起こすこともあります。 ●パルボウイルス感染症 ウイルスが腸に感染しておこる病気で、急性経過をたどり、嘔吐、下痢をおこし、死亡率も高い病気です。伝染力が高いのが特徴で、環境中に出たウイルスは6ヶ月〜1年間生存し、感染能力を持っています。環境中のウイルスは一般的な消毒薬や乾燥に対して強い抵抗性を持ちます。生後間もない子犬では心筋炎を起こして急死することもあります。 ●伝染性肝炎 アデノウイルス1型によっておこる肝臓が冒される病気で、肝炎を起こし、肝機能不全や出血症状を起こし死亡率も高いです。角膜の内皮細胞にも感染し、目の白濁を起こすこともあります(ブルーアイ)。 ●アデノウイルス2型感染症 アデノ1型を用いていた昔のワクチンは、副作用としてまれに角膜の白濁が起こりました。今のワクチンは2型ウイルス株を用いることにより副作用がおきないようになっています。2型ウイルスは咳などの呼吸器症状を起こすウイルスです。 ●パラインフルエンザ 咳などの呼吸器症状を起こすウイルスです。人のインフルエンザとは別のもので、人への感染はありません。人のインフルエンザも犬にはうつりません。 5種混合ワクチンには上記の5つが入っています。レプトスピラは野外で移る病気であり、最初の接種後はまだ外に出られるわけではないので、最初は5種で充分です。その後、2回目のワクチンの際にレプトスピラを入れたものをうつかどうかを選んでもらいます。しっかり抵抗力が付いて外に行っても大丈夫になるのは2回目のワクチン後の2週間後からです。 コロナウイルスも入っている8種といわれるものはミドルタイターというタイプなので、当院では子犬においてはハイタイタータイプである、5種もしくは7種ワクチンを接種しています。 ●レプトスピラ(インターロガンス型・カニコーラ型。7種、8種に入っています) 細菌感染によって起こる病気で、野生動物(主にネズミ)から移ることが多いです。山、河、その他のアウトドアによくいくコは予防しておいた方がいいでしょう。いくつかの亜型がありますが、一般的にはインターロガンス型、カニコーラ型の2つが入っていることが多いです。 症状は嘔吐、下痢、腎炎、黄疸、死亡です。人畜共通伝染病であり、感染した犬の尿を通じて人も感染します。 ●コロナウイルス(6種、8種に入っています) 下痢を起こす病気ですが、一般には軽度ですむことが多いです。ただ、パルボウイルスと同時感染を起こすと症状がより重篤になることが知られています。人に移ることはありません。 予防さえしていれば死なずにすんだのに・・ということが数多く見られます。また病気になってから治療するよりも、ワクチンの費用の方が少なくてすみます。成犬では1年に1回ですみますのでしっかりワクチンを続けていきましょう。 大切なワンちゃんが伝染病に感染しないように、ワクチンを接種しておくことをおすすめします。 |
|||

