| 犬の高脂血症 |
| 高脂血症というのは、脂質の輸送や代謝に障害があることによって、血液中に脂質が増加してしまう状態です。 病院の血液検査で測る総コレステロール値とはトリグリセリド(中性脂肪)とコレステロールを合計したものです。 トリグリセリドとコレステロールは通常、血液中で遊離して存在するのではなく、タンパク質と結びついたかたち(リポタンパク)で運ばれています。リポタンパクと結合できなかった分は遊離脂質となります。 リポタンパクは、大きくカイロミクロン、VLDL、LDL、HDLに分けられます。 |
||||||||||
| それぞれのリポタンパクはトリグリセリドとコレステロールを含みますが、その比率が異なります。 カイロミクロンは腸から吸収された脂質を肝臓に輸送する役目を担っています。 |
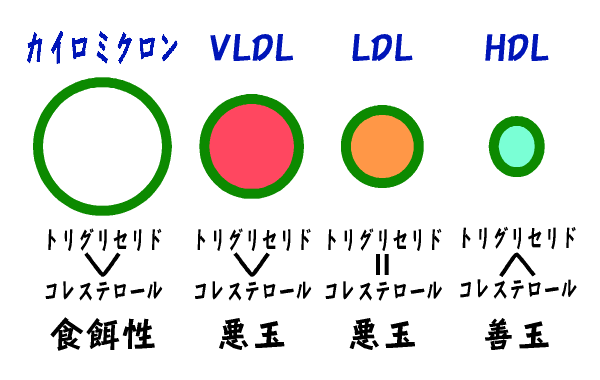 |
|||||||||
肝臓に運ばれた脂質は、VLDL、LDL、HDLに変換され、体に運ばれて組織の代謝に用いられます。 よく人では善玉、悪玉という表現をします。それはLDLが体にコレステロールを運ぶ役目、HDLが体からの余分なコレステロールを回収する役目を持っているからです。 人間ではLDLがリポタンパクのうちの3/4を占めますが、犬ではHDLが優勢となっています。このことは犬で動脈硬化、心筋梗塞が少ない原因のひとつでもあります。 高脂血症は以下のどちらかの状態と言うことができます。 1.リポタンパクのうちのどれかが増加している状態 2.リポタンパクに入れなかった脂質が血液中に増加している状態 総コレステロール値が高い場合には、トリグリセリドとコレステロールのいずれが高くなっているのか、4つのリポタンパクのどれが高くなっているのかを考えます。 ただ、リポタンパクの比率(悪玉:善玉)は、人では心臓疾患のリスク評価に重要ですが、犬ではそれほど重要ではないとされています。 高脂血症ではしばしば血漿成分の白濁が見られますが、トリグリセリドは白く、コレステロールは透明ですので、 1.カイロミクロンやVLDLが増加 → 血漿は白濁 2.LDLやHDLが中心 → 白濁があまり見られない という傾向にあります。 まず除外しないといけないのは、食後に一過性になっている高脂血症です。カイロミクロンは食後10時間以内は血中に存在しています。 食後12時間経った時点で高脂血症が見られる場合には、食餌による影響は除外されます。 正常値は以下の通りです。いずれも12時間絶食のものです。 |
||||||||||
|
||||||||||
人間では、高脂血症は動脈硬化や心筋梗塞の原因となりますが、犬ではそういった病気はまれです。 犬で危険性のある状態として、トリグリセリド値が500を越えたときは急性膵炎を誘発する危険があるため医療処置が必要になります。 コレステロールの方は緊急事態にはなりにくいとは言われていますが、角膜の脂質沈着などをおこす可能性があります。300を越えると注意です。 総コレステロールの増加を引き起こす原因としては、原発性の特発性高カイロミクロン血症、特発性高コレステロール血症の他、他の病気に併発したものがあります。 総コレステロール値が高いときはそれ自体の持つ問題以外に、他の病気が基礎にある可能性を考える必要があります。 ・糖尿病(こちらを参照) カイロミクロンの代謝に関係しているインスリンが欠乏しているために、カイロミクロンが体内に残ってしまいます。糖尿病の管理を行います。 ・蛋白喪失性腎症(こちらを参照) 腎臓からタンパクが失われるためにリポタンパクの合成ができなくなってしまい、タンパクと結合できなかった遊離脂質が血中に増えます。 ・副腎皮質機能亢進症(こちらを参照) 高コレステロール血症が約30%の症例で見られたと報告されています。 ・甲状腺機能低下症(こちらを参照) 高コレステロール血症が症例の2/3で見られます。 治療法は、原因が分かったときにはその治療をします。高脂血症のコントロールとしては食餌療法や内服薬の使用を考慮します。 |
||||||||||

